こんにちは、うしです。
今回はこの抗生剤が処方されていたら注意ということで、業界では有名なあの観点から非医療者向けに書いてみます。
そもそも抗生剤(抗菌薬)とは、
体内の細菌(ウイルスではない)を減らす目的で使用するもの、と言ったらいいかなと思います。
ポイントは、細菌は体の中で良くも悪くも共存しており、全て死滅させることは害ということです。
具体的に言うと、
口腔内には口腔内の常在菌がいて、いい意味では口腔内環境を保ってくれています。これを抗生剤で死滅させると口腔内カンジダになったりします(悪いカビが生えたりします)。
大腸などにも善玉菌などいて、腸内環境を保ってくれています。抗生剤を使用するとこれらがいなくなり、CD腸炎などの薬剤性腸炎の原因になったりします。
これは後述します。
また、一度抗生剤で体中の死滅させると、その菌が復活する際に、耐性を持つ可能性があります。いわゆる耐性菌です。
イメージとしては、抗生剤使用してほぼ全滅に見えたけど、なんとか耐え抜いた抗生剤に強い菌が増殖していくイメージでしょうか(笑)
抗生剤にうるさい人は、主にこれらの副作用と耐性菌の点から不適切利用に注意を訴えてることが多いです。
以前風邪に抗生剤を出す理由というブログを書きましたが、
一般に、抗生剤を出した方がいいのかどうかは、医者でも悩むことが多いため、受診される側としては絶対わからないと思います。
今回は、その中でも、これらの抗生剤は吸収率の点で注意が必要、という側面で描いていきます。
大前提として、診察してもらい処方された薬は、その通りに飲むようにしてください。
(次回以降そこに受診するかは別として、自分のブログを読んだからもらった薬全部飲まないとかはやめてください(笑))
感染症診療の基本として、どの臓器に、なんて種類の菌が、どのような形態で、宿主の免疫がどの程度で、どのくらい悪さをしているかというものが重要になります。
例えば、普通の人が普通の肺炎になって、少しこじらして肺膿瘍(膿の塊)を作った場合、
肺という臓器に、たとえば肺炎球菌が(あまり膿瘍は作りませんが)、膿瘍を形成しており、宿主の免疫は普通、と言った感じです。
勘違いしやすいこととしては、感染症は抗生剤(や抗ウイルス剤)よりも宿主の免疫が大切で、もし膿の塊を形成していた場合は外科的に(手術などで)取り除くのが大切になります。
抗生剤がないと肺膿瘍は治療も難しく、また肺を手術するのは容易ではないため、比較的長期の抗生剤を使用することが多いです。
ここで抗生剤を使用する場合、先ほどの項目を考えて加味して、
なんの抗生剤を、どこから投与するか、というクエスチョンが生まれます。
例えば肺炎球菌の肺膿瘍(肺膿瘍は作りませんが例えとして)だとした場合、比較的安定していてかつ長期間になりそうなので(点滴でずっと投与するのは大変なので)
肺炎球菌に感受性があり、肺に移行性が高い抗生剤を、内服(飲み薬)で投与する
のような風になります。
●腸管の吸収率(=バイオアベイラビリティ)
ここまで難しい話をしてしまいましたが、
唯一簡単で、かつ重要なことがあります。
飲み薬の腸管の吸収率(=バイオアベイラビリティ)というものがあります。
これが、一般的にあんまり有名でないのですが、抗生剤も飲めば全部血液に吸収されるわけではないのです。
(ここからは分かりやすくするため( )で商品名も記載しますがご了承ください)
例えば
アモキシシリン(サワサリン) …80-90%
セファレキシン(ケフレックス)…90%
レボフロキサシン(クラビット)…99%
ST合剤(バクタ)…85%
などのものは吸収率だけみたらいいですが、
セフジニル(セフゾン)…16%
セフジトレン(メイアクト)…16%
セフポドキシム(バナン)…50%
セフィキシム(セフスパン)…50%
セフカペン・ピボキシル(フロモックス)…20-30%?
(Burke A, et al. Antibiotics Essentials. 12th edition, 2013)
は吸収率がとても悪いです。
16%なんて、7分の1しか吸収されないではないですか(笑)
そして、何となく聞いたことあるものも多いのではないでしょうか?
これらの吸収率の悪い抗生剤こそ、日本ではよく処方されているようです。
いずれにしても、感染臓器が腸管などでないならば、腸から吸収されて血液に薬剤が移行しなければならないため、
成分が同じならば腸管の移行性がいい抗生剤の方が絶対いいです。
そもそも、内服の方が点滴よりも量はずっと少なくなる傾向にあります。
7分の1しか吸収されないということは、元々の添付文書の適正使用量は必要量の7倍多く見積もられているのでしょうか?
詳細は知りませんが、少なくても、腸管移行性の悪い抗生剤を1st チョイスすることはまずないため、これらの薬を処方する(される)ときは注意が必要とは言えます。
●MRSA腸炎とは
一部医療者向けの話になりますが、
MRSAという、メチシリン耐性黄色ブドウ球菌というものがあります。
抗生剤に耐性もった強いブドウ球菌(という種類の菌)ということですね。
MRSA腸炎というのは、その菌に感染した腸炎という病気であり、日本の医師国家試験にも以前に出題されています(何年度かは忘れましたが)。
この病気、実は海外では全然ないらしいです。
科学的にMRSA腸炎は存在しないと立証したわけではないですが、
きっかけは、どうやら日本では、外科の周術期の患者さんによく上記の腸管吸収率の悪い抗生剤を創部感染予防に使用していたそうです。
すると、多くの患者が下痢をしたそうです。
広い意味では抗生剤の副作用でしょう。
便培養を出すと、そこにMRSAという菌がいたためMRSA腸炎と診断し、MRSAという菌に効く抗生剤は非常に限られるため、バンコマイシンを内服で使用し、改善したとのことです。
ただしこれにはからくりがあって、
ざっくりいうと、腸管吸収率の悪い抗生剤を使用して、腸内細菌が死滅し、腸管に残ったのはMRSAの他にCD(Clostridium difficile)というかの有名な菌の主に2種類と思われます。またこのCDという菌は空気に触れる培養では育ちにくいため、便培養で検出されることは珍しいです。
またこの2種類の菌どちらもバンコマイシンという抗生剤内服は有効です。
おそらく、腸管移行性の悪い抗生剤を内服して、MRSAとCDの2種類の菌のみ残り、MRSAはただ存在しただけで、CDがCD腸炎として悪さをし、便培養ではCDは育たずただ存在だけしたMRSAのみ検出され、あたかも腸炎の起因菌がMRSAと勘違いさせ、バンコマイシンを使用したら(本当はCD腸炎に効いているのに)MRSAも菌が消え、腸炎の症状も消え、あたかもMRSAの腸炎のように見えていたのだと思われます。
こういう腸管移行性の悪い抗生剤を使用するのは日本くらいらしくだからMRSA腸炎という診断(概念)が海外で乏しいのだと思われます。
(こちらの出展は、岩田健太郎先生の感染症講座でのレクチャーをもとに記載しています)
これらの真偽かどうかという問題ではなく、言いたいことは
7分の1しか吸収されない抗生剤は、7分の6は腸管に襲い掛かるため、薬剤性の腸炎をきたしやすいということです。
●抗生剤処方の例外(小児中耳炎を例に)
とは言っても処方される経緯は人それぞれなので、
診察を受け処方された薬剤はしっかり飲みましょう。
診療科によって例外はあり、特に内科以外の領域ではスタンダードが異なります。
その一例として、小児科領域の中耳炎を上げてみます。
中耳炎とは、ざっくり言うと耳の中に細菌感染がおきてしまう病気で、耳鼻科の領域です。
耳鼻咽喉科というように喉の菌が例えば耳管などを経由して感染してしまうようで、ある意味常在菌(そこにいて普通の菌)であり、菌を死滅させなくてもいいようです(菌が減ればよい)。
そういう前提からか、1st チョイスは前述の腸管移行性のよいアモキシシリンなどなのですが、それ以外の選択肢として、セフジトレン(メイアクト)を推奨するとガイドラインでも記載があります。
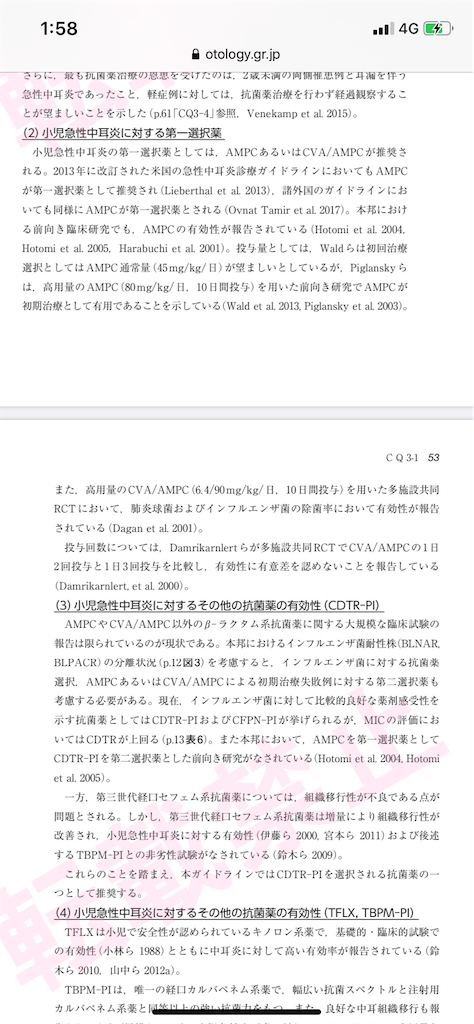
(小児急性中耳炎診療ガイドライン 2018版参照)
どうやら腸管吸収率以外に、耳への移行性の問題や、使用時の治癒率などから、それなりに推奨しているようです。
このように、腸管の吸収率だけでなく、感染臓器への移行率なども重要なため、一概には言えません。
ただし、このセフジトレン(メイアクト)も2番手以下の薬剤なので、腸管吸収率の悪い薬剤が第一選択になることは少ないとは言えると思います。
また小児科領域自体も特殊です。結構移行性の悪い抗生剤を使用している印象があります。
これは、若いため薬剤性の腸炎などになりにくいほか、赤ん坊に積極的な臨床研究を仕向けることも少なく、また小児中耳炎のガイドラインにもあるように(子供は中耳炎が多いため)、腸管移行性よりも治療経験的に使用することが多いのではないかと思います。
(あとは、親御さん含め念のため、という安心もあるとは思います)
少しでも参考になれば幸いです。
スヤア
